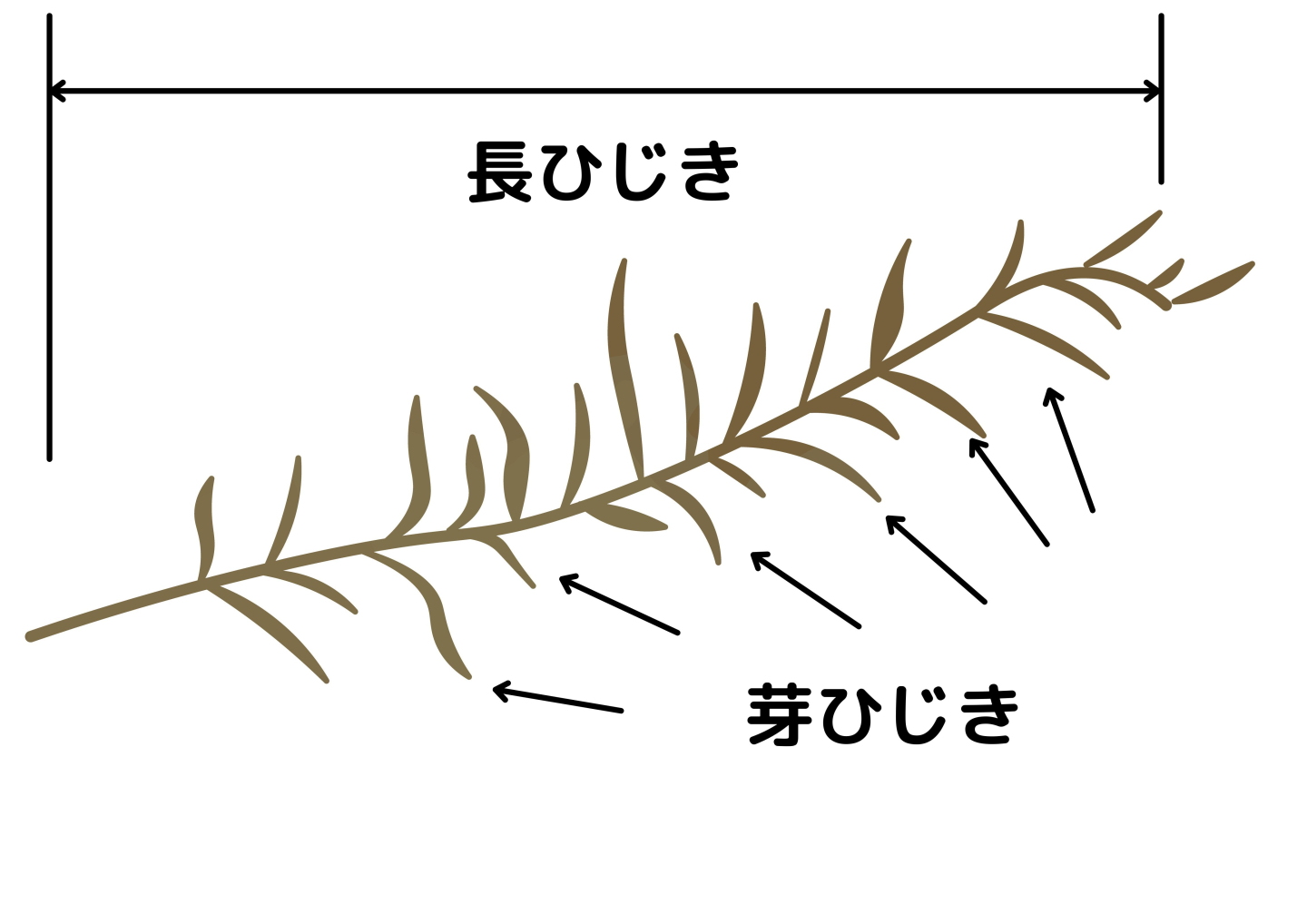[学校法人大和学園]
大和学園地域健康栄養支援センターが「食物アレルギーと上手に付き合う方法~子どもの笑顔を守る安全で安心な食の未来~」をテーマとして設立記念講演会を開催します。
2023年4月に設立3周年を迎える大和学園地域健康栄養支援センター。コロナ禍で延期を余儀なくされていた設立記念イベントをいよいよ実施します。「食物アレルギーと上手に付き合う方法~子どもの笑顔を守る安全で安心な食の未来~」をテーマとして、アレルギー専門医と管理栄養士による食物アレルギーセミナーをお送りします。
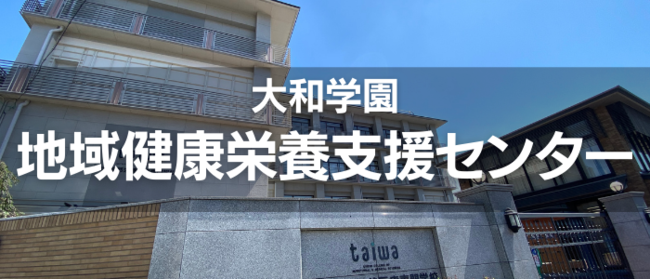
大和学園地域健康栄養支援センターは、地域に密着して栄養や健康の課題解決を図りながら、健康長寿社会の実現をめざすため、2020年4月に開設されました。栄養講座、健康料理教室、子育て支援、 食物アレルギー対応事業、高齢者栄養ケア、スポーツ栄養等の事業を通じて生活習慣病の予防と健康増進のための啓発活動や食・栄養に関する情報発信を行います。またセンター事業を通じて得られる成果を、養成教育の教育・研究に活用することで、より実践的な専門職業人の養成に取り組んでいます。
2021年4月には、センター内に「認定栄養ケア・ステーション」を開設し、地域密着型で食・栄養に関わるさまざまなサービス(食事の相談や料理教室・講習会などさまざまな事業)を行ってきました。
●「認定栄養ケア・ステーション」とは
「認定栄養ケア・ステーション」は、公益社団法人日本栄養士会が進めている事業であり、栄養ケアを提供する地域密着型の拠点として、地域住民・自治体・健康保険組合・民間企業・栄養士養成校・医療機関・薬局などを対象に、栄養相談、特定保健指導、セミナー・研修会への講師派遣、調理教室の開催など、食・栄養に関する幅広いサービスを展開していくものです。
2023年4月、大和学園地域健康栄養支援センターは設立から3周年を迎えます。コロナ禍により延期が続いていた設立記念講演会を、この度いよいよ開催することとなりました。テーマは「食物アレルギーと上手に付き合う方法~子どもの笑顔を守る安全で安心な食の未来~」とし、アレルギー専門医で当センターのセンター長を務める伊藤節子、そして当センター所属の管理栄養士で日本栄養士会認定の「食物アレルギー栄養士」としても活動する森久美子が講演を行います。会場での直接参加に加えて、オンラインでも参加が可能なハイブリッド形式で開催します。ぜひご参加ください!
日 時:2023年2月5日(日)13:30~15:30(13:00受付開始)
会 場:【来場】京都栄養医療専門学校(定員60名)
【WEB】YouTubeライブ(定員200名)
参加費:無料

講演I:「食物アレルギーの起こる仕組みを知り、健康的な食事を考える」
講 師:伊藤 節子(大和学園地域健康栄養支援センター長/小児科専門医/日本アレルギー学会指導医)
【伊藤講師より】卵や牛乳などの食物アレルギーと上手く付き合うための食事の工夫を学びます。今回は「みんなで一緒に食べること」がテーマです。食事の大切さや健康的でおいしい食事とは何かを一緒に考えてみませんか?

講演II:「食物アレルギーがあっても実現できる豊かな食生活」
講 師:森 久美子(大和学園地域健康栄養支援センター管理栄養士/食物アレルギー栄養士)
【森講師より】生涯にわたって大切な”食べる力“=”生きる力“。食物アレルギーと上手く付き合いながら”食べる力“を育む食生活について、離乳食の進め方や食育をテーマにお話します。
参加申込:下記URLから必要事項を入力の上、お申し込みください。
https://forms.gle/oET6xLGhWTZbSMDn8
申込締切:2023年2月1日(水)
お問合せ:学校法人大和学園 京都栄養医療専門学校 地域健康栄養支援センター
TEL 075-872-8500(担当:教育支援部)
〒616-8376 京都市右京区嵯峨天竜寺瀬戸川町18
●京都栄養医療専門学校について
厚生労働大臣指定管理栄養士・栄養士養成施設、日本病院会認定校。高度な実践力とホスピタリティマインドを兼ね備えた管理栄養士、栄養士、医療事務、医療秘書、診療情報管理士の養成に努めています。
◆管理栄養士科[4年制]
https://www.kyoto-eiyoiryo.ac.jp/course/kanri/
◆栄養士科[2年制]
https://www.kyoto-eiyoiryo.ac.jp/course/eiyou/
◆医療事務・医療秘書科[2年制]
https://www.kyoto-eiyoiryo.ac.jp/course/jimu/
◆診療情報管理士科[3年制]
https://www.kyoto-eiyoiryo.ac.jp/course/shinryou/
●学校法人大和学園について
学校法人大和学園は1931年創立。京都市内に京都調理師専門学校、京都栄養医療専門学校、京都製菓製パン技術専門学校、京都ホテル観光ブライダル専門学校の4つの専門学校とラ・キャリエール クッキングスクールを展開。「栄養、医療・福祉、調理、製菓・製パン、食育、ホテル、ブライダル、ツーリズム」分野の職業教育を提供し、専門知識と技能やホスピタリティマインドと人間力を兼ね備えたスペシャリストを養成しています。
https://www.taiwa.ac.jp/
企業プレスリリース詳細へ (2023/01/16-12:46)
大和学園地域健康栄養支援センターが設立記念講演会「食物アレルギーと上手に付き合う方法」を開催します!:時事 ... - 時事通信ニュース
Read More